“プロダクトを作る力”だけでは、いまや市場で勝ち残れない。PdM(プロダクトマネージャー)が機能・ロードマップを設計し、PMM(プロダクトマーケティングマネージャー)が市場導入と成長戦略をリードする“二頭体制”が世界標準になりつつあります。ところが日本では、PMMはまだ「聞いたことはあるけれど実態がわからない」職種でした。
そこでアイスリーデザインは、日本で初めてPdMとPMMの二頭体制を広めるべく、 「PMM Japan Community(PJC)」 を立ち上げ、実践知を凝縮したホワイトペーパー 『PMM完全解説ガイド』 を同時リリースしました。本記事では、その背景と狙い、PMMが変える開発とマーケティングの未来、そしてコミュニティが描くロードマップを余すことなくお届けします。
なぜ今、PMMなのか──設立に至った3つの課題を深掘りする
1-1 “届ける力”の欠落──機能は作れるが、市場に届かない
日本のテック企業は、PdM(プロダクトマネージャー)が率いる開発組織の成熟度が高く、「要件を固め、確実に作り切る」フェーズには定評があります。ところが、完成した機能やサービスが “ユーザーに見つけられず、使われず、愛されず” に終わる例が後を絶ちません。
理由はシンプルです。「誰に、どのような価値を、どう伝えるか」をリードする専門職が不在だからです。開発チームはリリース後の利用定着や市場拡張まで担い切れず、営業・マーケ部門はプロダクト内部の意思決定の経緯を知らないままキャンペーンを打つ。結果、機能が“埋もれる”構造が常態化していました。優れた技術やUXを持ちながら、市場で真価を発揮できない。この“届ける力”の欠落が、成長の阻害要因となっています。
1-2 断片情報しかないPMMナレッジ──「知らない」「学べない」の悪循環
グローバル市場では2010年代からPMM(プロダクトマーケティングマネージャー)の役割が標準化し、機能・価格・ポジショニングを緻密に設計してSaaSを急成長させる事例が数多く生まれました。しかし日本語で体系的に学べる資料はごくわずかで、「PMMってマーケと何が違うの?」 という初歩的な疑問さえ、ネット検索では片手で数えるほどしかヒットしません。
当社が2025年5月に行った調査では、LinkedInに存在する「PMM」を冠する国内グループはわずか41件。ほとんどが採用要件に関するもので、ほとんど交流もなく、ベストプラクティスが断片的にしか共有されていません。結果として、各社が独学・属人的にロール設計を試みるものの、定着せずに頓挫する。そんな “知らない・学べない”悪循環 が続いていました。
1-3 PdMとPMMの連携不全──ねじれ構造が生む疲弊と機会損失
もう一つのボトルネックは、PdMが市場の声と開発マネジメントを両肩に背負い、疲弊していることです。本来PdMは「プロダクトを成功に導くCEO」として見られますが、市場分析・ペルソナ設計・競合調査・GTM施策・KPIモニタリングまで“ワンオペ状態”では、開発フェーズに割くリソースが削られ、どちらも中途半端になりがちです。反対にビジネスサイド側はプロダクトの意思決定過程にアクセスできず、リリース後に表層的な広告やPRを打つだけ。このねじれ構造が続けば、開発とマーケの相互不信を招き、ローンチ後の改善サイクルも回りません。
これらの課題を一挙に解決する鍵が、PdM(作る責任者)とPMM(届ける責任者)の連携フレームワークです。PMMの導入は、作る力と届ける力を融合し、日本のプロダクトを“作って終わり”から“市場で勝たせる”ステージへ引き上げる必須条件なのです。
PMM Japan Communityが掲げるビジョンと3つの提供価値
ビジョン──「PMMを日本企業の“当たり前”にする」
私たちが目指すのは、PdMがプロダクトを“作る力”を磨き、PMMが“届ける力”をリードすること。その2つが車輪のように噛み合う企業文化を日本に根付かせることです。企画・開発・マーケティングが縦割りで動く時代はもう終わりました。PdMとPMMが並走し、市場・顧客のインサイトを起点にプロダクトを成長させる姿を「当たり前」にする。それがPMM Japan Community(PJC)の存在意義です。
2-1 知見の集約と可視化──“明日から使えるPMMライブラリー”
国内外の成功例・失敗例を余すことなく収集し、実務家がすぐ参照できるデジタルライブラリーを整備していきます。戦略キャンバス、ローンチ計画表、ペルソナ雛形などのテンプレートはすべて無償公開。「PMMを任されたが何から始めればいいかわからない」――そんな担当者でも翌朝から社内説明に使える“即戦力ドキュメント”で、知識の属人化を解消します。
2-2 ロール設計とキャリアパスの標準化──“リファレンスモデル”を共有
PDCAを素早く回すには、役割の線引きを曖昧にしないことが肝心です。PJCではPdM/PMMの典型的職務分掌とKPI設計をリファレンスモデル化。たとえば「PMMが持つべき北極星指標(North Star Metric)」や評価面談で使うコンピテンシーマトリクスをボードメンバー企業の実例付きで公開していきたいと思います。これにより、「PMMの評価軸が曖昧で昇給基準を作れない」という組織課題を一気に解消し、透明なキャリアパスを提示します。
2-3 共創型ハンズオン支援──“PoCを共に走る”コミュニティ
テンプレートと理論だけでは現場は動きません。PJCでは定期勉強会やワークショップを開催し、必要に応じて伴走支援も実施。成果物はコミュニティ全体でレビューし合い、横串のピアレビュー文化を醸成します。「情報は得たが実行できない」壁を突破し、参加企業同士で成果を底上げするエコシステムを育てます。
PJCはこの3つの価値提供を通じて、“作る力×届ける力”を兼ね備えた日本型PMMモデルを形成し、国内プロダクトの競争力を根底から押し上げていきたいと考えています。
PMM Japan Community 参加登録はこちらから
> PMM Japan Community(PJC)参加受付のご案内
ホワイトペーパー『PMM完全解説ガイド』──国内初のPMMに関する実践知を体系化
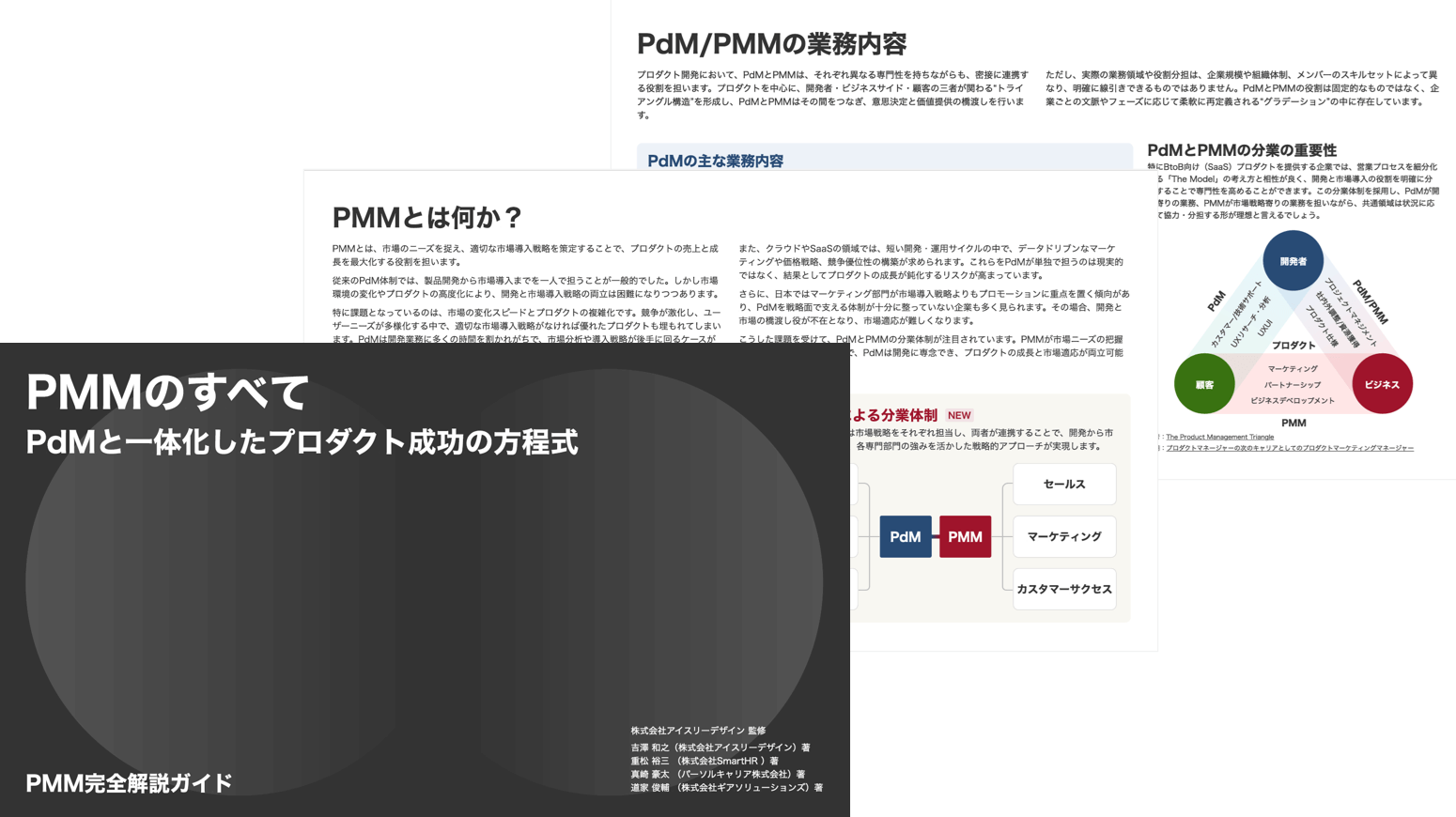
私たちがこのホワイトペーパーを世に出した最大の理由は、「日本にはPMMを導入・運用するための共通フレームワークがほぼ存在しない」 という構造課題を放置できなかったからです。米国では2010年代に PMM の職能が急伸し、数多くの実践ガイドやテンプレートが公開されています。一方、日本企業の現場では、
- 会社ごとに 役割とKPIがバラバラ――社内で「PMMって結局何をする人?」という議論に毎回立ち戻る
- 書籍・資料は散発的で、体系だった導入ステップが共有されていない
- PdM、マーケ、営業、CSのあいだで責任範囲が曖昧になり、リリース後の改善サイクルが継続しない
という“フレームワーク空白”が常態化していました。結果、せっかくPMMを採用しても属人的に回す → 異動・退職 → 再び手探り という負のループが起き、組織知として蓄積されない――これが国内ITプロダクト産業の成長速度を鈍化させる隠れたボトルネックになっています。
そこで私たちは、「ないなら作ろう」「しかも実務家がすぐ使える形で標準化しよう」と決めました。『PMM完全解説ガイド』はその第一歩です。
収録した内容例:
- PMMが必要とされる市場背景
- PdM/PMM分業モデル
- 組織設計・導入ステップ
- GTM戦略&プロモーション事例
こうした“共通言語”をオープンにすることで、企業間でノウハウをコピー&ペーストできる土台をつくり、PMMを日本のスタンダードに引き上げたい――それがホワイトペーパーに込めた私たちの狙いです。今後はコミュニティに寄せられるフィードバックを反映し、年度ごとに改訂版を公開していく予定です。標準化は一朝一夕で完成するものではありません。だからこそ私たちは、まず“芯となる型”を投下し、みなさんと一緒に磨き上げていくプロセス自体を開示していきます。
ホワイトペーパーダウンロードはこちらから
> PMMのすべて ーPdMと一体化したプロダクト成功の方程式-
PdM×PMMで実現する“届ける力”とコミュニティ拡張計画
私たちがめざすのは、華やかなバズワードや一過性の大舞台ではなく、知を持ち寄り、磨き合い、現場で再現するための“土壌”そのものを耕すことです。PMM Japan Communityでは、定期的なミートアップや小規模ワークショップ、さらには年に数回のカンファレンスを通じて、PdM/PMMの実務者が立場や企業規模を越えて集い、課題と学びをリアルタイムで交換します。
そこでは成功事例だけでなく、うまくいかなかった試行錯誤や途中経過も包み隠さず共有し、「失敗を財産に変える」文化を育てたいと考えます。集まった知見はテンプレートやチェックリストとして公開し、参加企業が翌朝から自社プロダクトに適用できる形で循環させる——この小さな実践のループを積み重ねることで、PdMが“作る力”を、PMMが“届ける力”を互いに補完し合い、日本のプロダクト全体がユーザーに届く確率を一段引き上げること。それこそが私たちの本当のゴールであり、コミュニティ形成に込めた一番の想いです。
みなさんもぜひ、このコミュニティに参画してみてください。
まずは壁打ちから ― PdM/PMM体制のご相談を承ります
私たちアイスリーデザインは、”作る力”と”届ける力”を両輪で回すPdM/PMM体制を、戦略立案から運用まで一気通貫で共創します。
― 市場と開発のギャップを埋める役割設計
― 再現性のあるGTM・KPI運用の内製化
― 横断型チームを動かす実践的ハンズオン
これらを通じて、貴社のプロダクトが持つポテンシャルを“機能の完成”で終わらせず、市場で確実に伸ばし続ける仕組みへ昇華させます。
「開発は強いが市場成長が頭打ち」「部署間の足並みが揃わない」といった悩みがあれば、ぜひ一度ビジョンや課題をお聞かせください。まずはアセスメントをするところから始め、最適な体制と戦略を一緒に描きましょう。
アイスリーデザインが提供するPdM/PMM体制実行支援の詳細はこちら
> PdM/PMM体制実行支援サービスページ




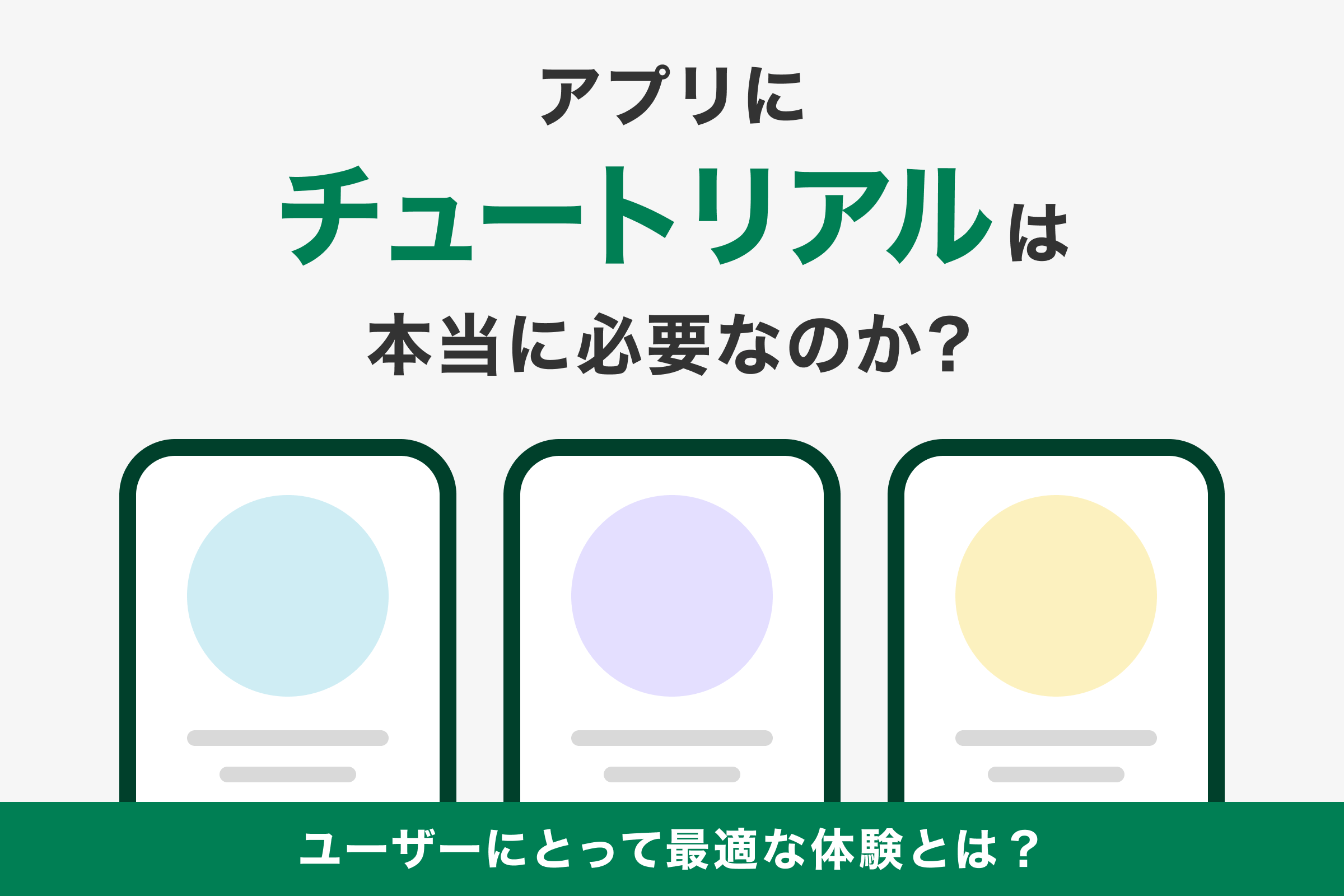
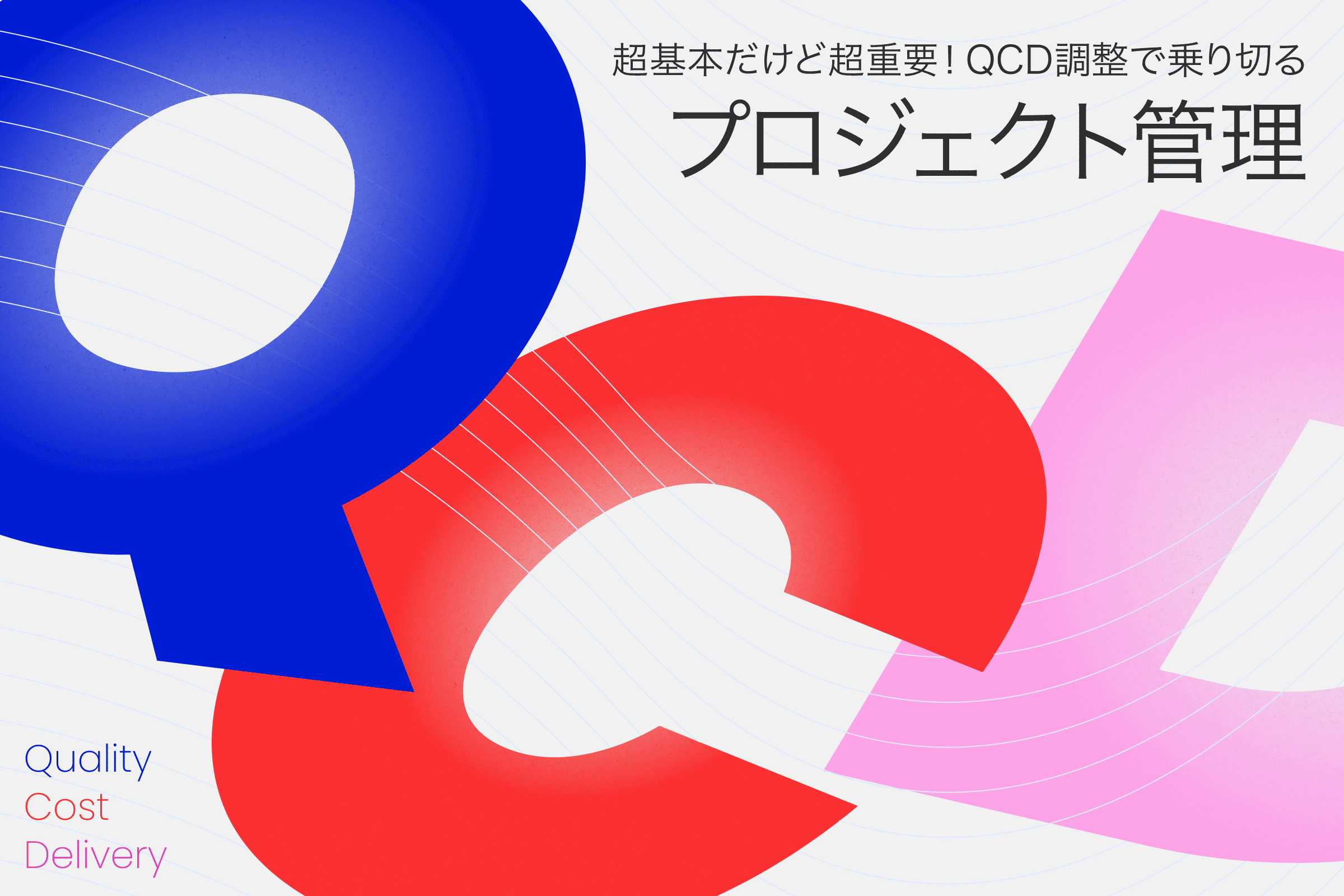
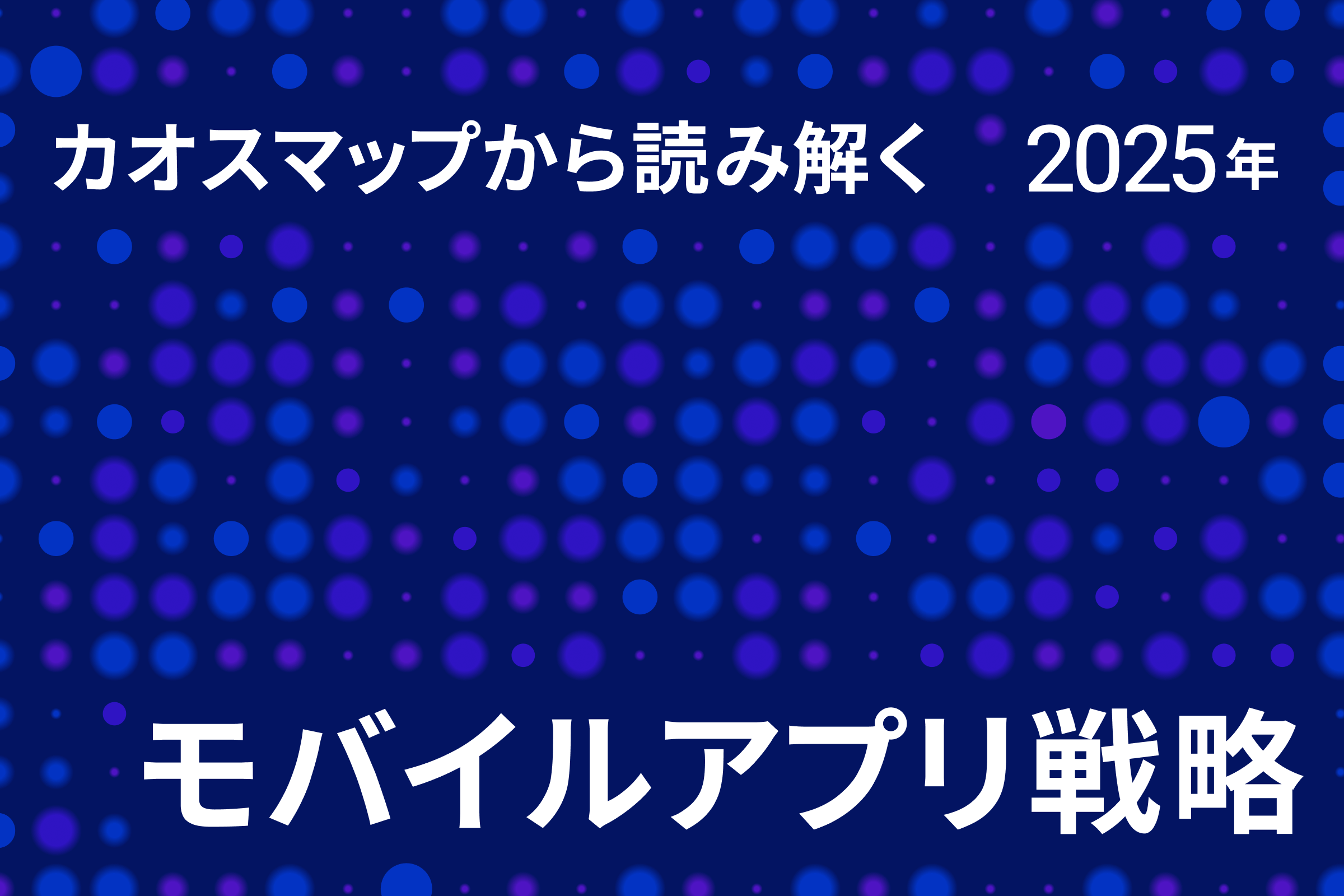

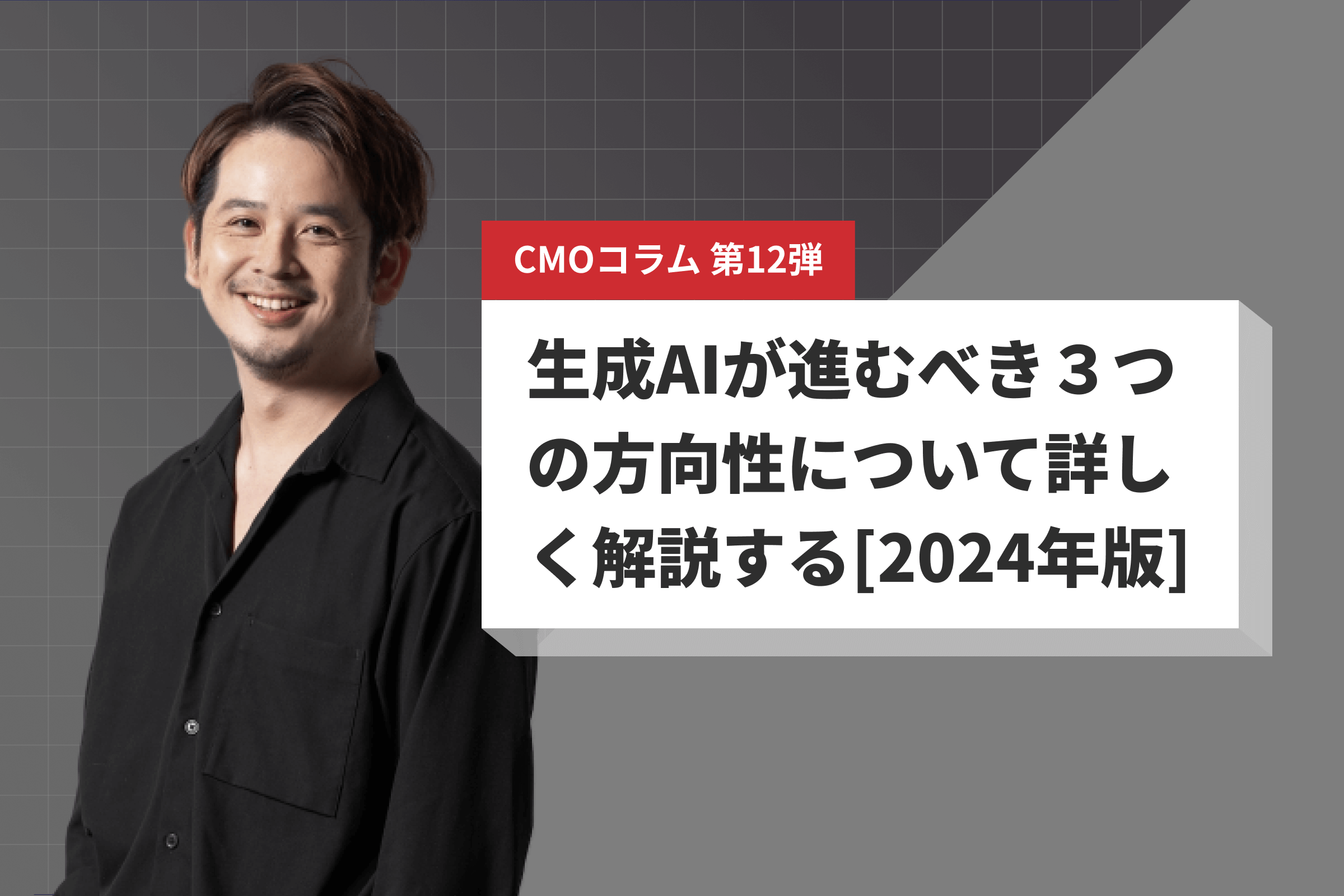


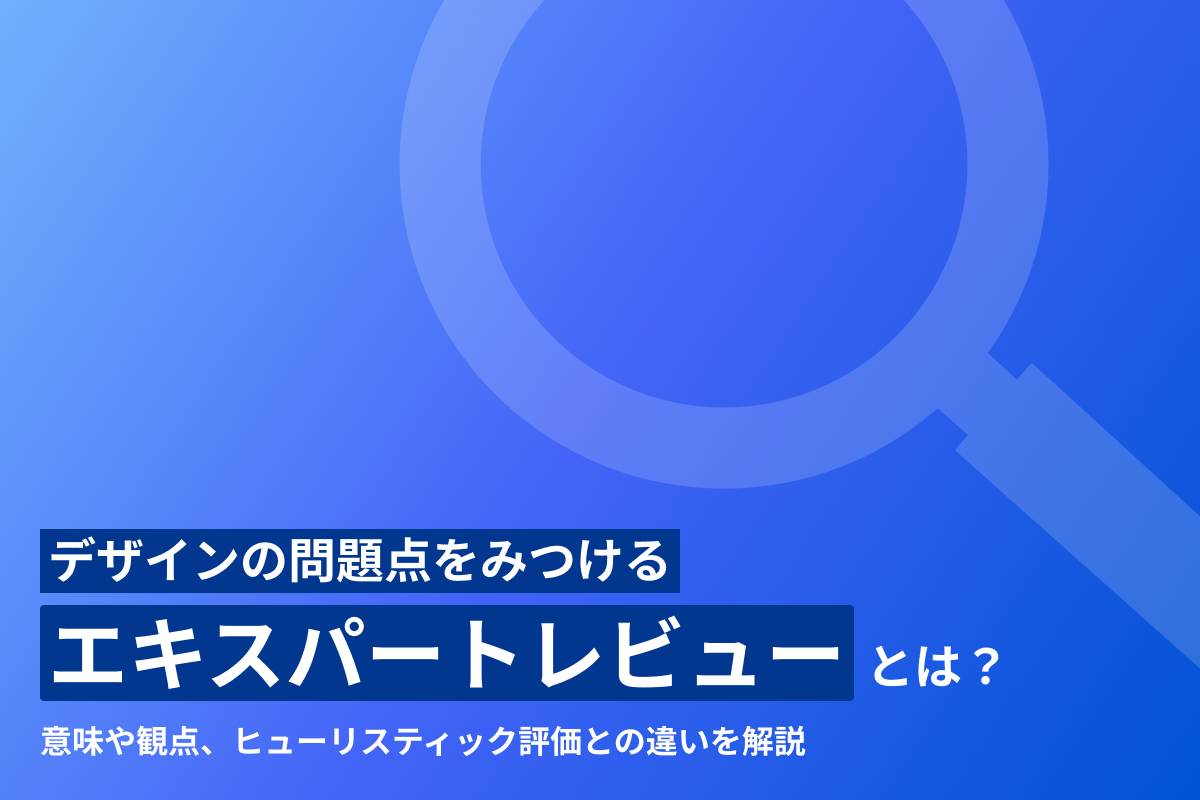

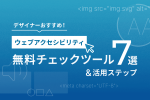

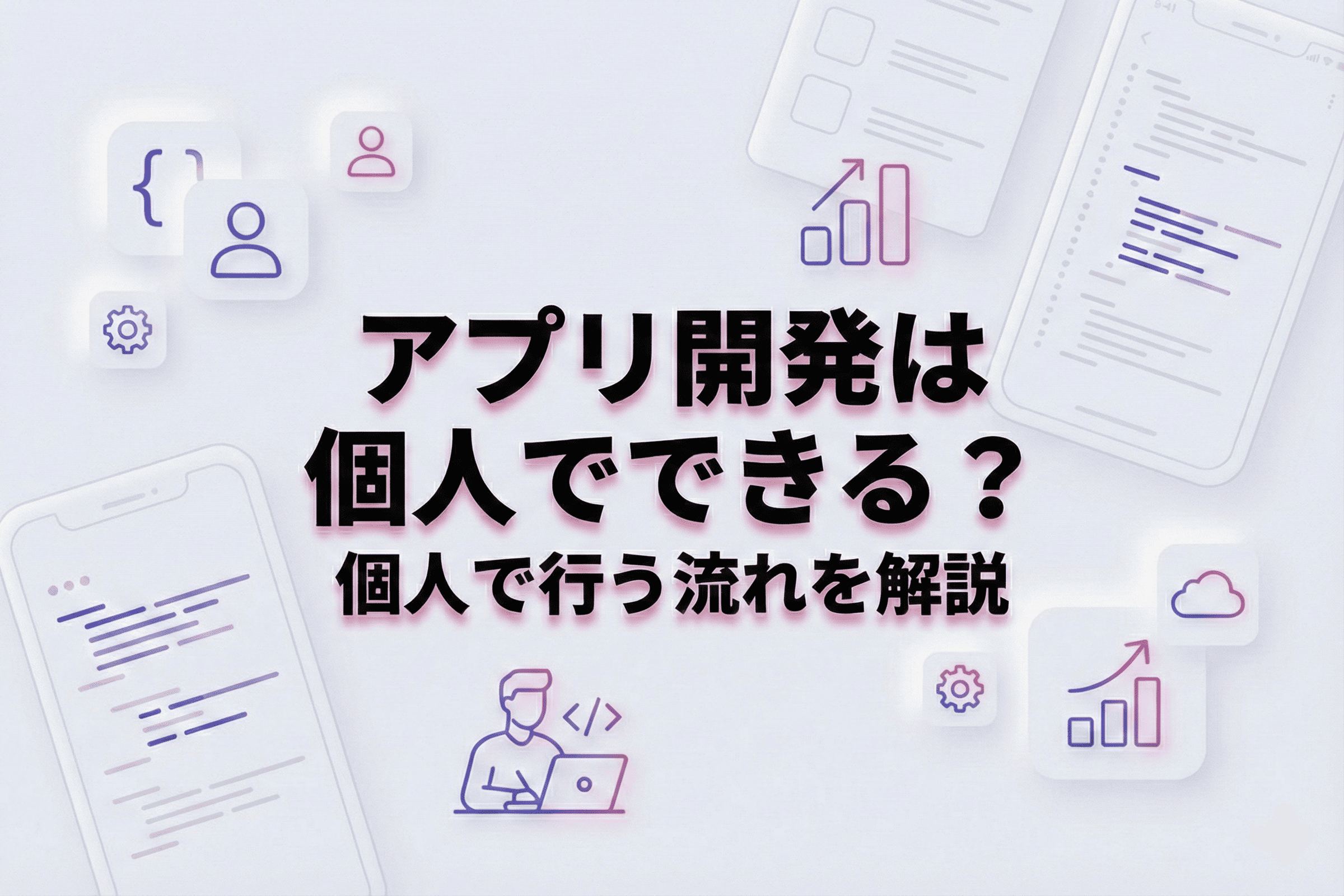
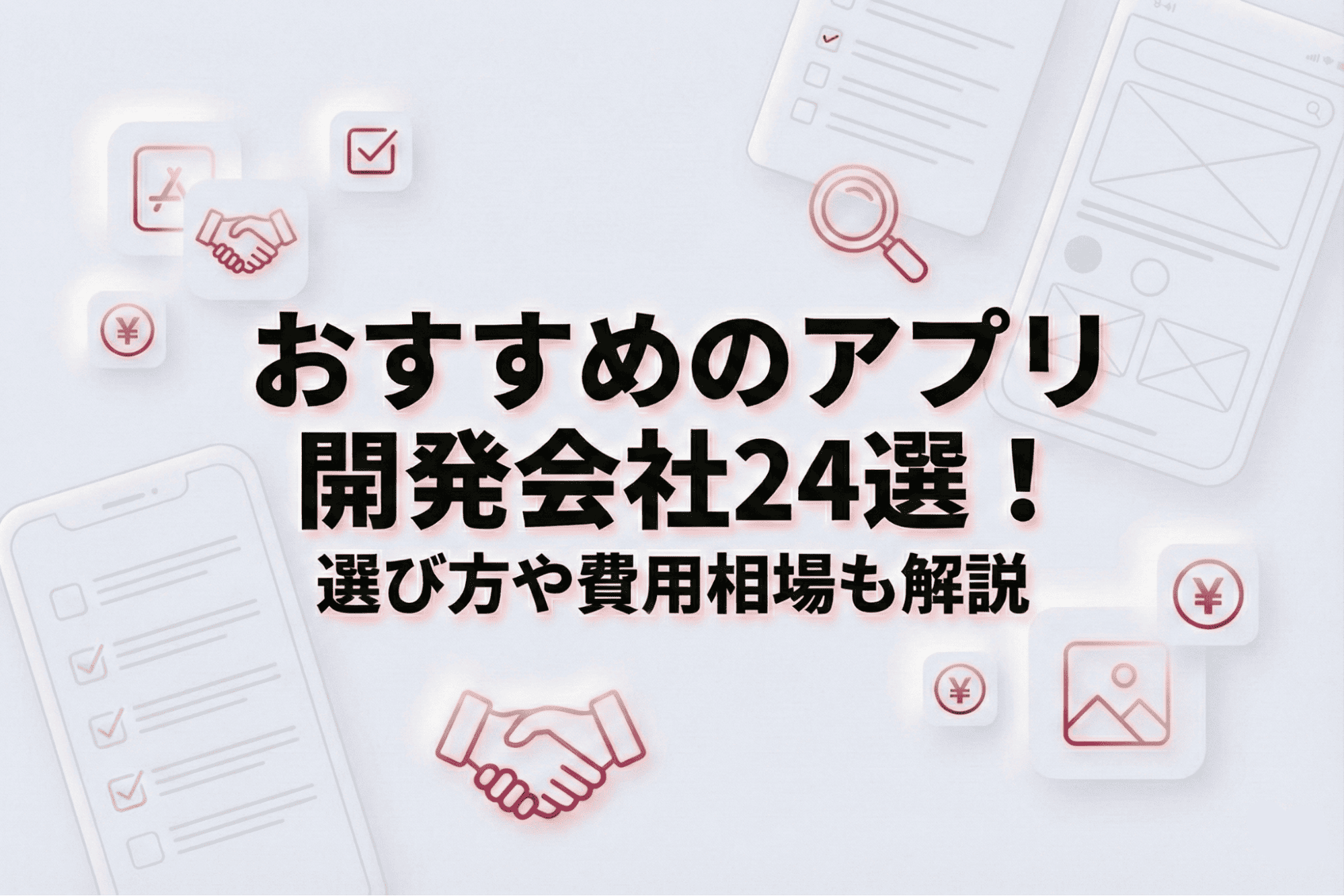
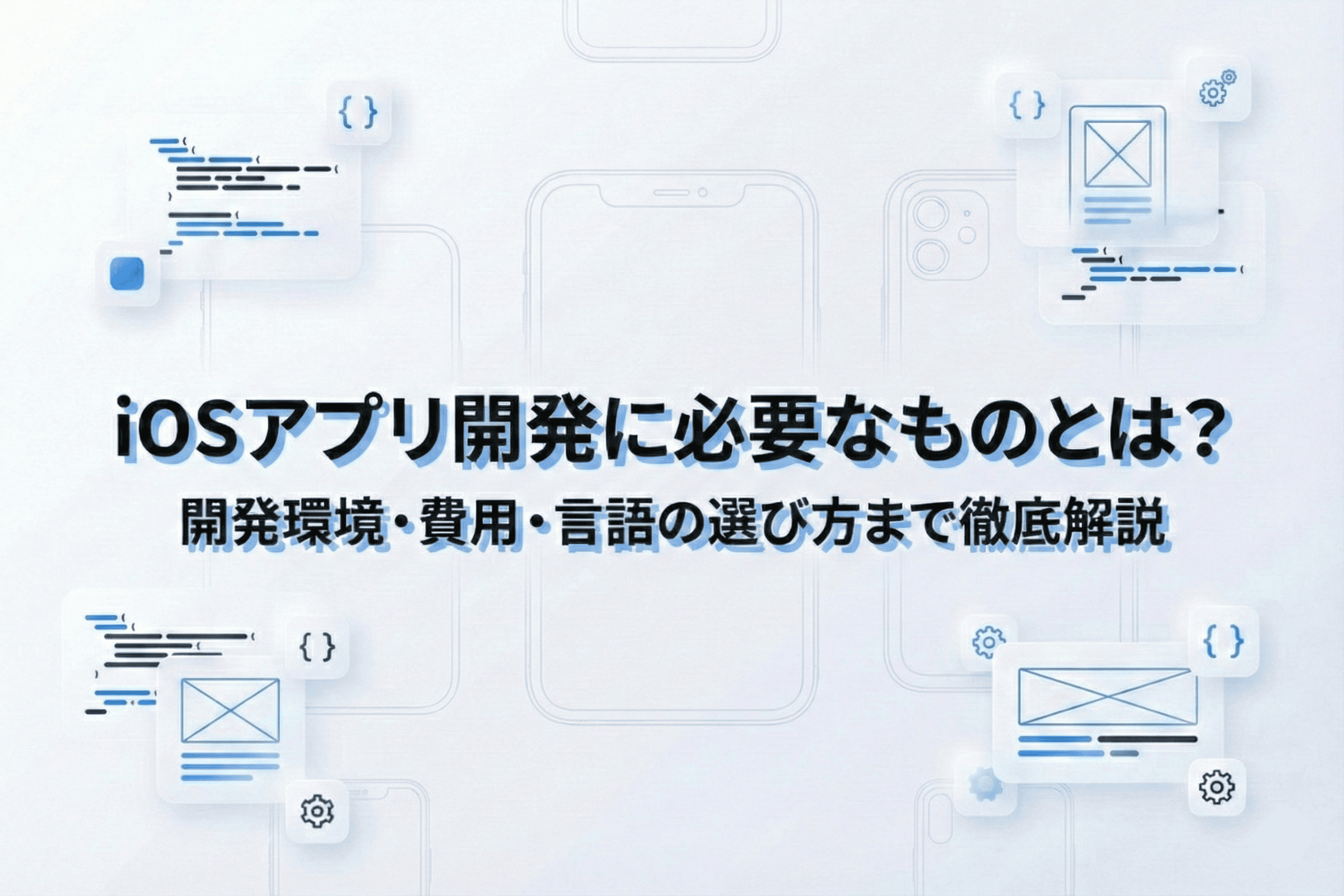
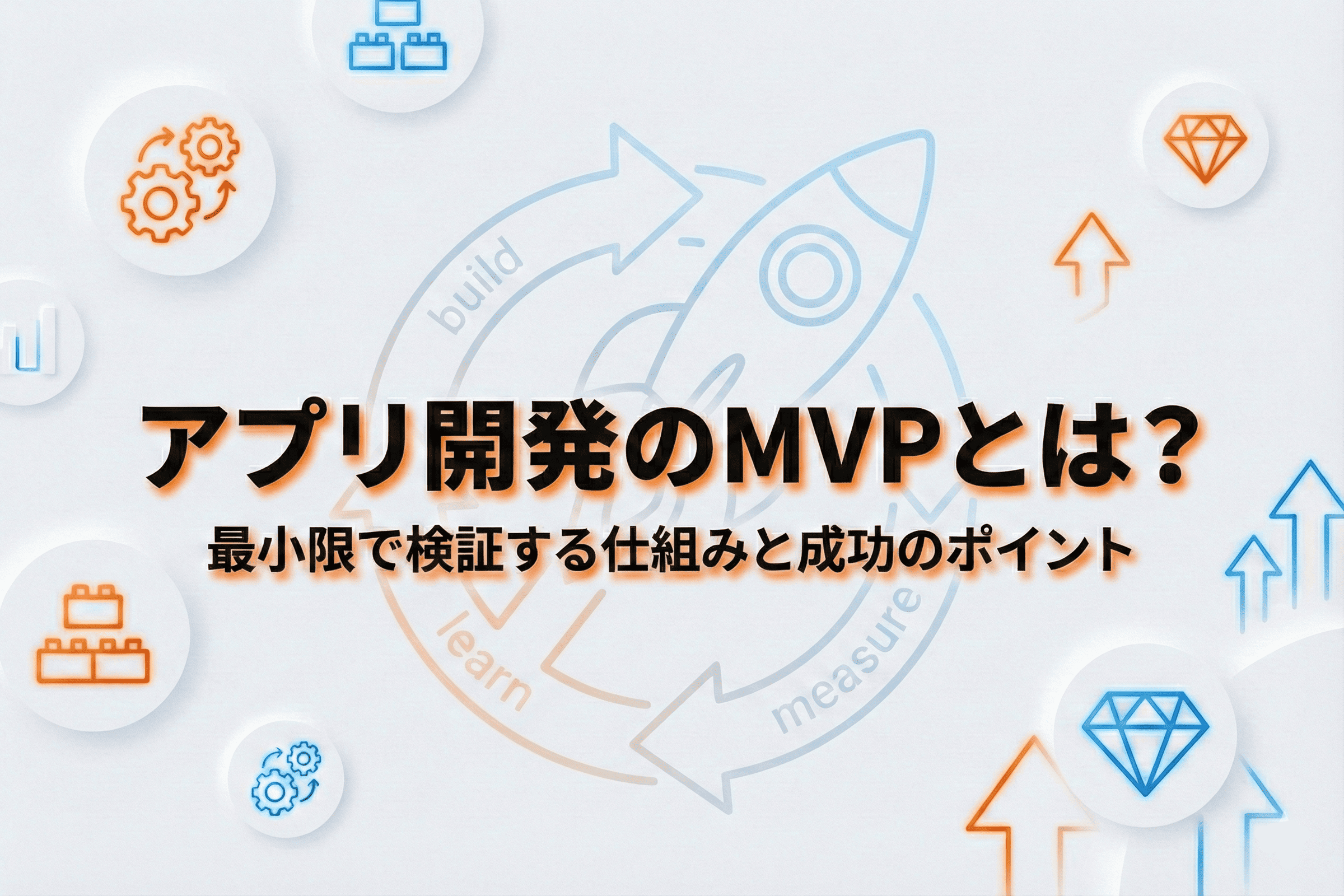
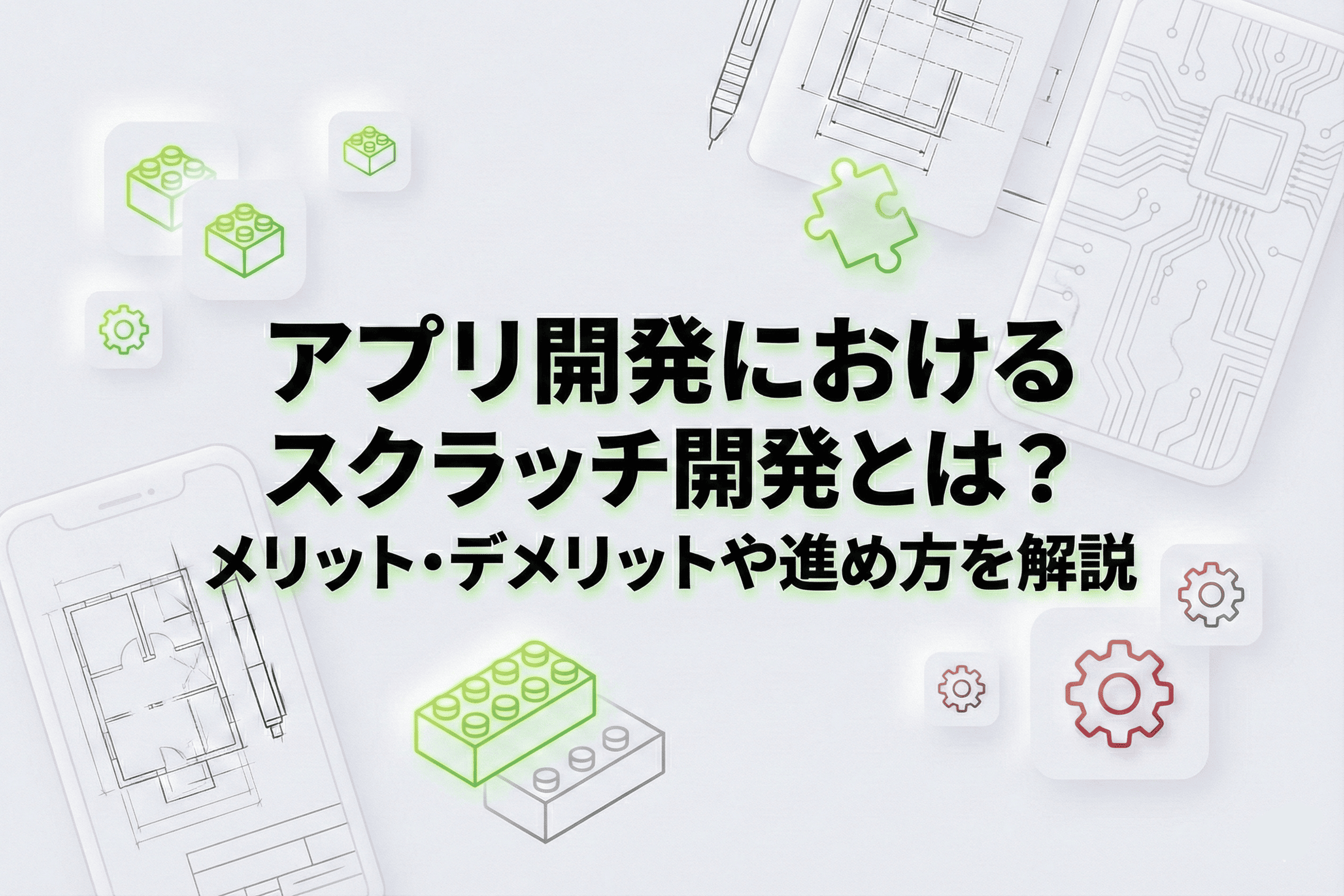
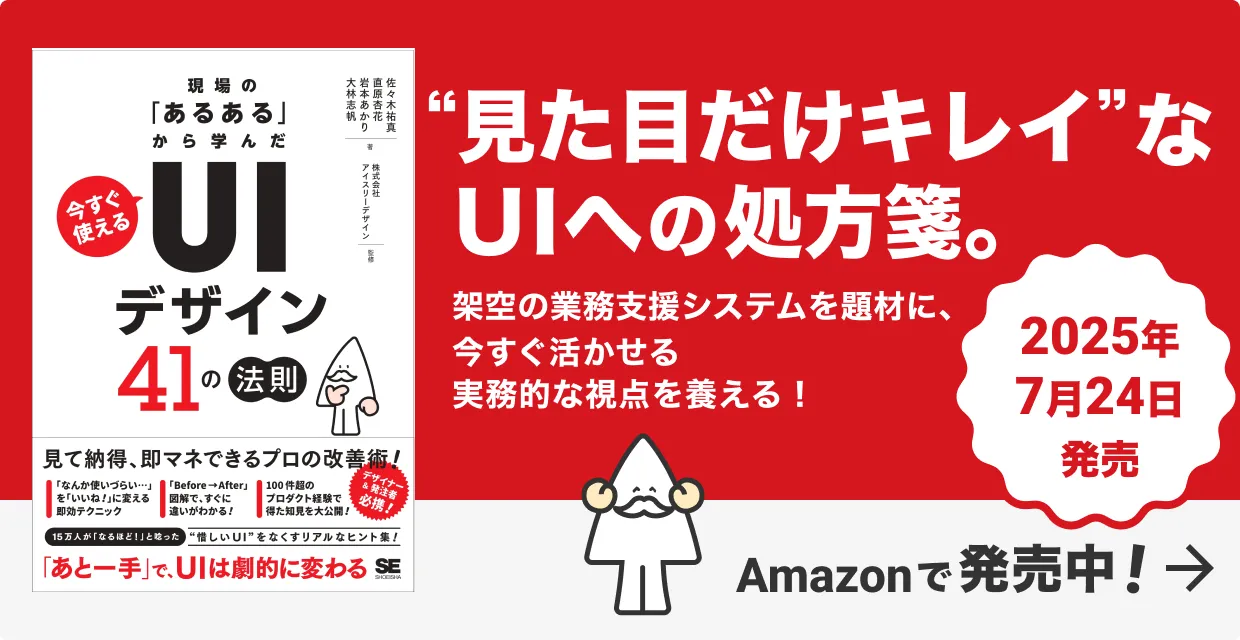
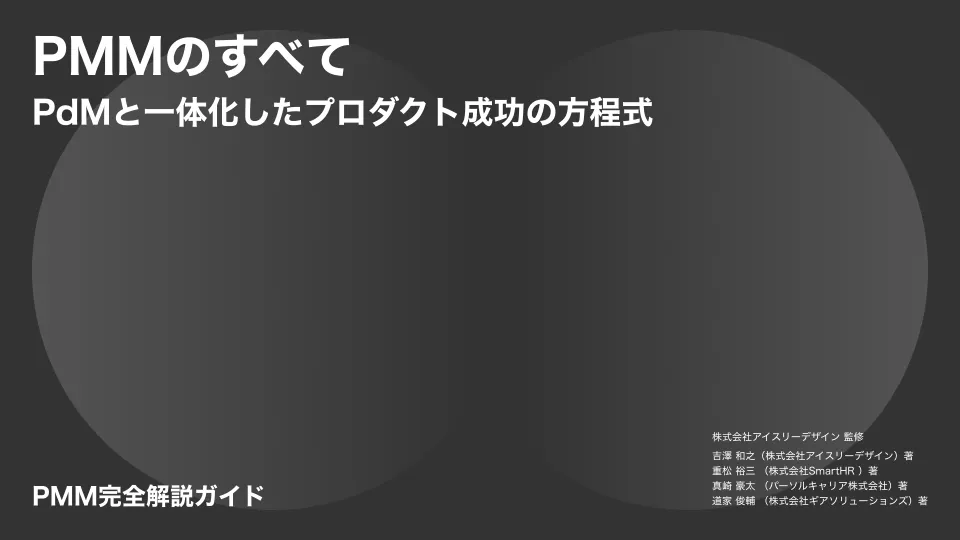
> PMMのすべて ーPdMと一体化したプロダクト成功の方程式
(※コミュニティへお申し込みいただいた方には、資料はプレゼントさせていただいております。)