私たちは、エンジニアリングの考え方・判断基準・価値観をまとめたEngineering Handbookを公開しました。
このハンドブックは、私たちがどのような姿勢で開発に向き合い、どのような判断基準で技術を選択し、何を大切にしているかを言葉にしたものです。
多くの企業が技術的なドキュメントを内部資料として管理する中で、なぜ私たちはこれを外部に公開するのか。
それは、透明性こそが信頼の基盤であると考えているからです。
私たちと関わるクライアント、これから一緒に働く仲間に、「私たちがどのように考え、どのように動くか」を知っていただきたい。
そして、その判断基準が一貫していること、変化に対応しながらも軸がぶれないことを、言葉として残したいと思いました。
このハンドブックは完成形ではありません。むしろ、対話の出発点として機能するものだと考えています。
Engineering Handbookをつくった理由
ここ数年で、チームの人数も、関わるプロジェクトの規模も大きく変化しました。
新しい仲間が増え、若いメンバーが次々と加わり、案件の幅も広がりました。
私たちは今、“組織としての成長期”にいます。
これまでは、見渡せる範囲にすべてのプロジェクトがあり、直接やりとりしながら判断を合わせていくことができました。
しかし、組織の成長とともに、それには限界が見えてきました。
実際に、私自身がほとんど関わらないプロジェクトも増え、もはやすべてを把握することは難しくなっています。それは少し寂しさもありますが、同時にチームが自律的に動けるようになってきた証でもあります。
だからこそ、どんな状況でも同じ方向を向けるよう、「私たちはなぜこうするのか」という共通の考え方を言葉にしておきたいと思いました。
Whyを共有することで組織を強くしたい
このハンドブックでは、特定のチームのやり方や成功事例を語っているわけではありません。
私たち全員に共通する、「なぜそうするのか(Why)」という考え方を中心に、できる範囲で言葉にまとめました。
アジャイルな進め方もあれば、ウォーターフォール型の進行もあります。
プロジェクトの性質や顧客の状況によって、最適な形はそれぞれ異なります。
私たちはクライアントワークという性質上、毎回まったく違う文脈に向き合うことになります。
だからこそ、私たちにとって重要なのは、どの手法を取るかではなく、「何のためにそれを選ぶのか」を共有することです。
技術も仕組みも、最終的には「顧客に確実に価値を届ける」ための手段であり、その“目的への一貫性”こそが、チームの強さの源になります。
私たちはこの考えを共通の言葉として残すことで、プロジェクトやチームを越えて同じ方向を向くようにしたいと思いました。
暗黙の文化を、共通言語にする
これまで私たちは、日々のやりとりやプロジェクトの現場の中で自然と文化を育んできました。
Slackでのオープンな会話、コードレビューでの丁寧な議論、顧客に価値を届けるための試行錯誤。そうした小さな積み重ねが、私たちのチームを形づくってきたと思っています。
ただ、その多くは「なんとなくうまくいっている」「暗黙の了解」で回っている部分がありました。
メンバーが増え、プロジェクトが増えるにつれて、それらを“言語化しないまま伝える”ことの難しさを感じるようになりました。
「誰が見ても同じように理解できる形で、文化を残すにはどうすればいいか?」それを形にし、支えるための試みとして、このEngineering Handbookをつくりました。このハンドブックは単なるマニュアルではなく、私たちの考え方・判断基準・行動の背景を共有するためのドキュメントです。
それを言葉として残すことで、次に入るメンバーも同じ価値観をもとに動けるようになる。
そして、文化そのものが「チーム全体の知」として継承されていく。
そんな循環をつくりたいと考えました。
AI活用も、ドキュメント文化の一部として
今回のハンドブックづくりは、AI活用や開発標準化と同じ文脈の中にあります。
AIを「使うもの」としてだけでなく、「チームで考え、共有し、使いこなしていくための知」として位置づけたいと思っています。
私たちは、要件定義・設計・実装・レビュー・ドキュメント化まで、あらゆる工程にAIを取り入れる試みを進めています。
それは効率化のためだけではなく、より創造的な時間をチーム全体に取り戻すための仕組みです。このハンドブック自体も、AIの支援を受けながらまとめました。
AIが人の代わりに書くのではなく、考えを整理し、言葉にするための相棒として活用しています。
そしてこの記録が、今後のメンバーがAIをより良く使いこなすための道しるべにもなっていくはずです。
完璧ではなく、「最初の一歩」として
このハンドブックは、最初から完璧を目指したものではありません。
まだ荒削りな部分もありますし、書ききれていないことも多くあります。
けれど、まず形にして、そこから育てていくことにこそ意味があると考えています。
私たちは「完成された答え」よりも、「対話を通じて磨かれていくプロセス」を大切にしています。ドキュメントもまた、その一部です。
書くことは考えることであり、共有することは学び合うこと。このハンドブックは個人のものではなく、エンジニア全員の共有財産です。
誰もが意見を出し、手を加え、より良いものにしていく。
そうしてはじめて、「文化として根付く」ものになると思っています。
このハンドブックが意味すること
クライアントの皆さまへ
このハンドブックを外部に公開することは、私たちにとって一つの約束です。
私たちがどのような考え方で開発に向き合い、どのような基準で判断しているかを知っていただくことで、安心してプロジェクトを任せていただける関係を築きたいと思っています。
このハンドブックに書かれた判断基準は、すべてのプロジェクトに共通する私たちの姿勢です。
プロジェクトの性質に応じて手法は変わっても、「顧客に価値を届ける」という軸はぶれません。
透明性のある開発プロセス、一貫した品質基準、継続的な改善姿勢。
これらすべてが、確実な価値提供につながります。
これから一緒に働く仲間へ
このハンドブックは、私たちの文化を知るための入り口です。
どのような価値観を持ち、何を大切にし、どのように成長していくか。
それを事前に知ることで、「自分がこのチームで働くイメージ」を具体的に持っていただけると思います。
私たちは完璧な組織ではありませんが、常に改善し続ける姿勢を持っています。
そして、その改善に参加してくれる仲間を歓迎します。
最後に
このハンドブックは、組織を良くするための最初の一歩です。
これをきっかけに、ドキュメントを残すこと、言葉で文化を共有することが当たり前になれば、
私たちのチームはもっと強く、もっと柔軟になっていくはずです。
文化は、掲げるものではなく育てるもの。
そして、その出発点がこのドキュメントであり、これから先に続くすべての取り組みだと思っています。
「書くこと」は、考えること。
そして、書いたものを共有することは、文化を未来に手渡すことだと信じています。


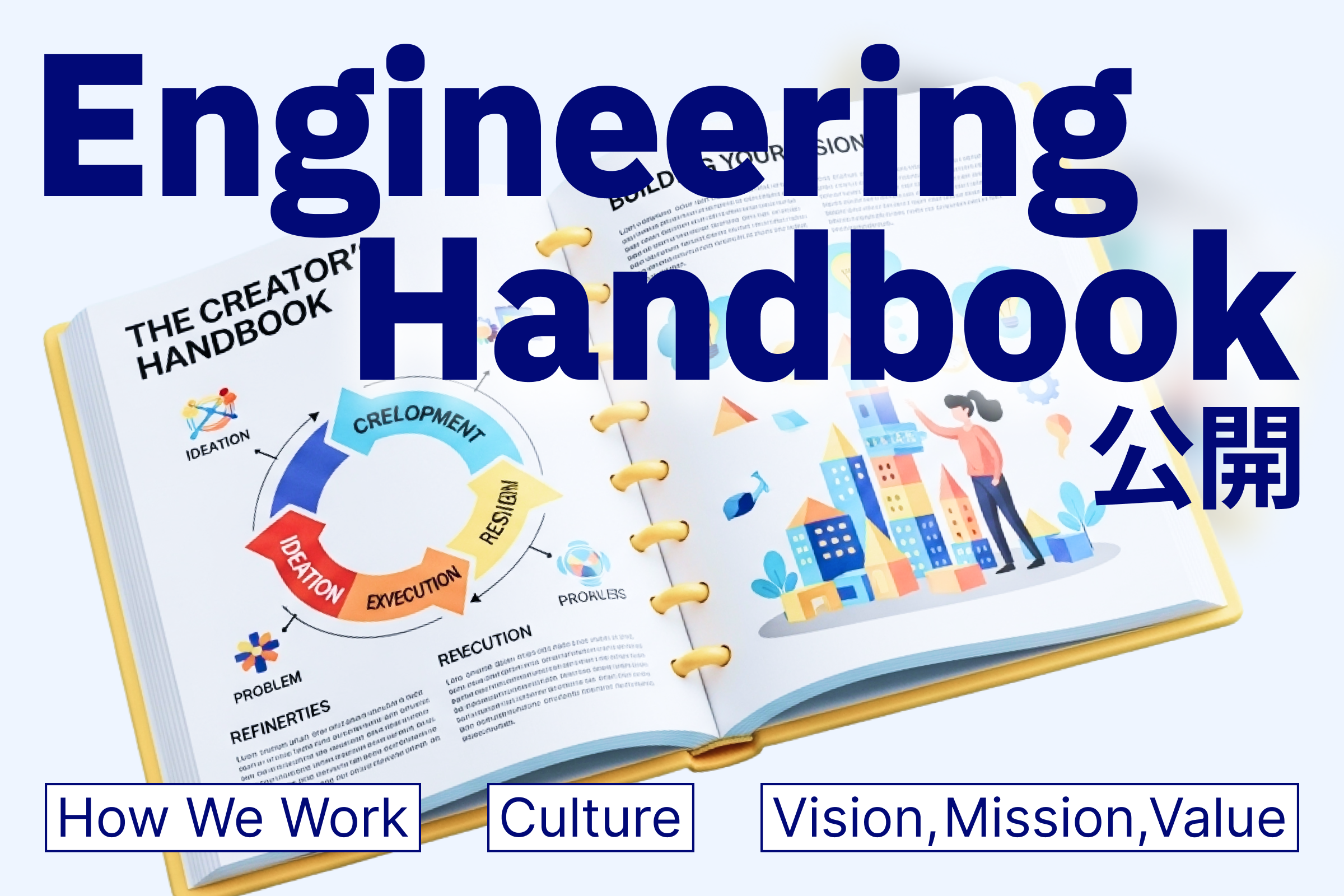
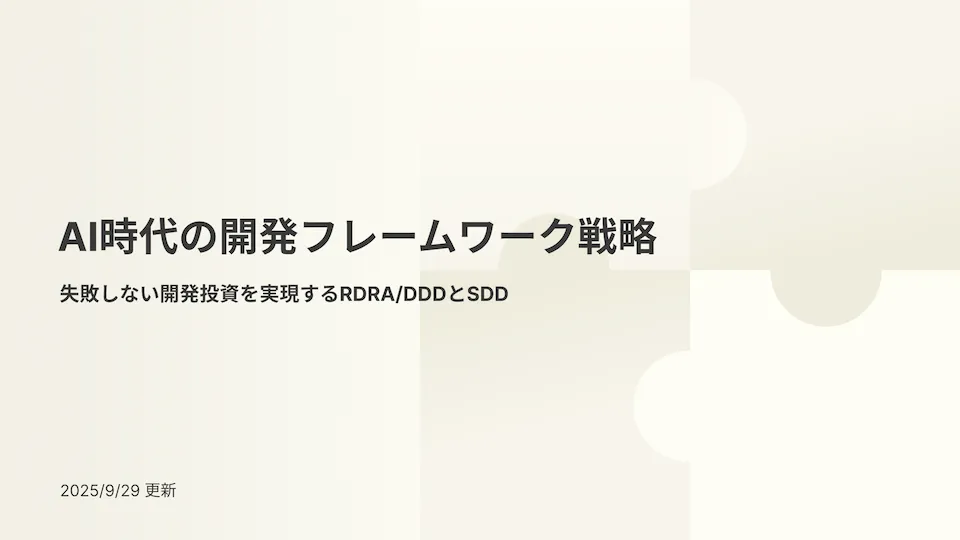
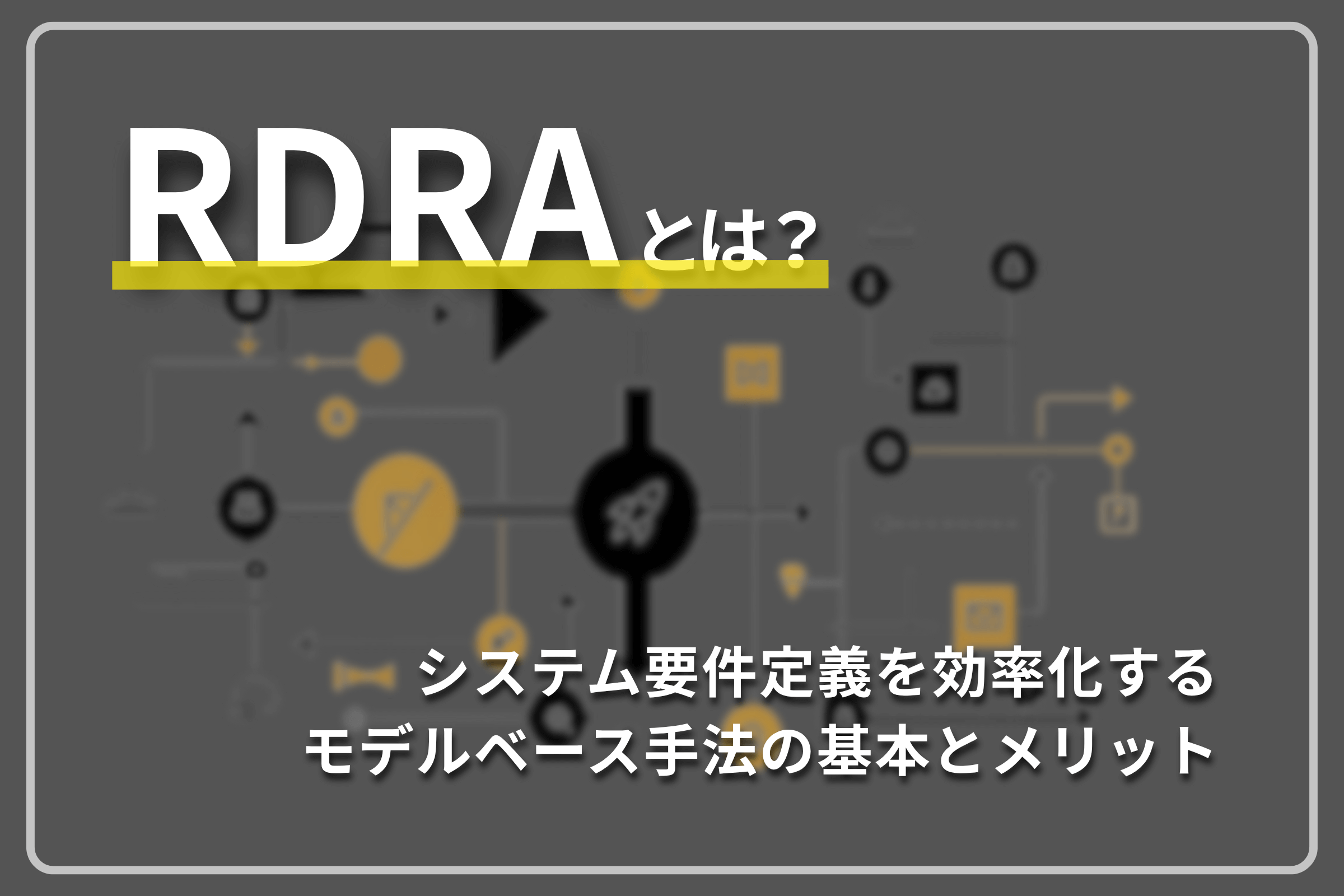




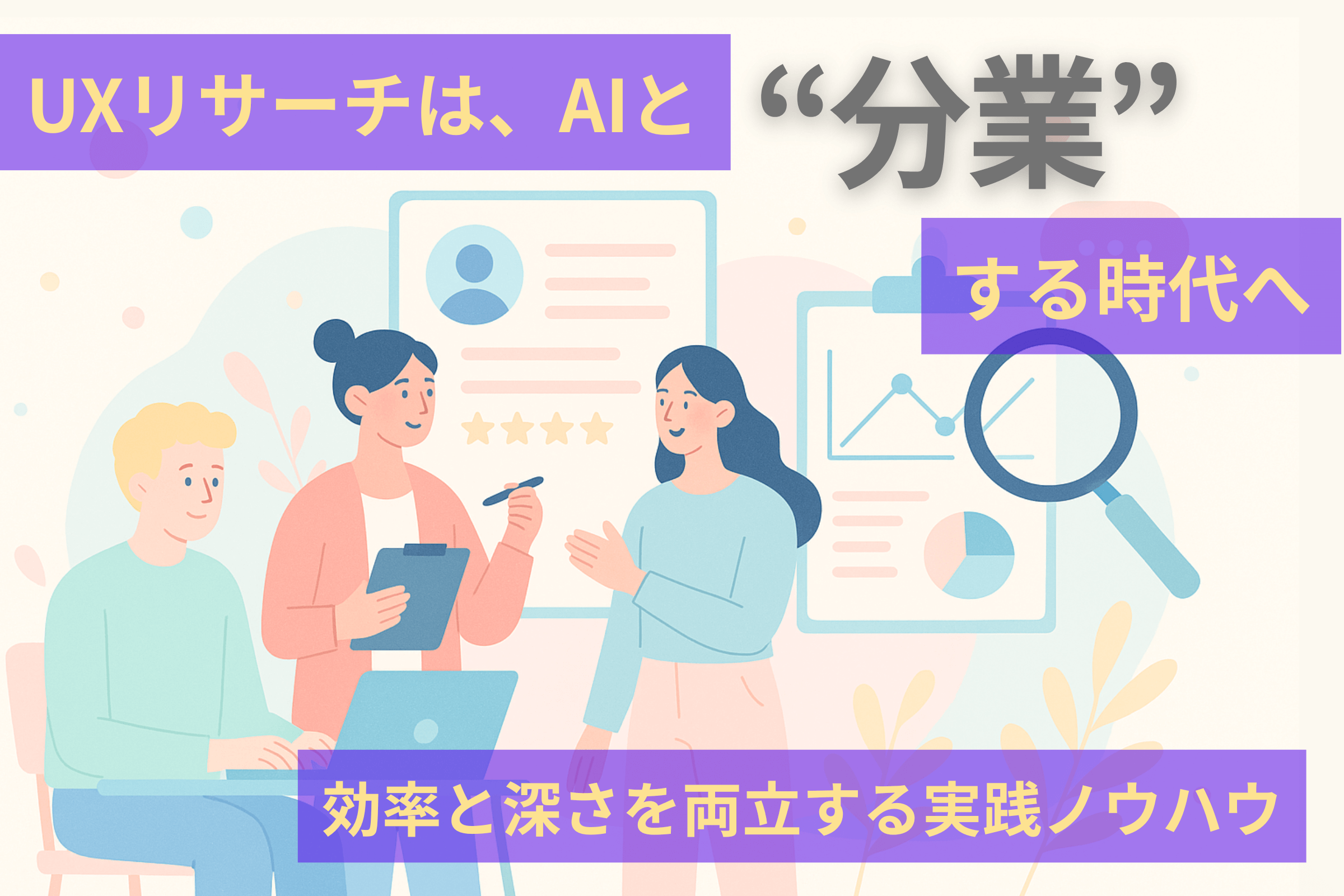
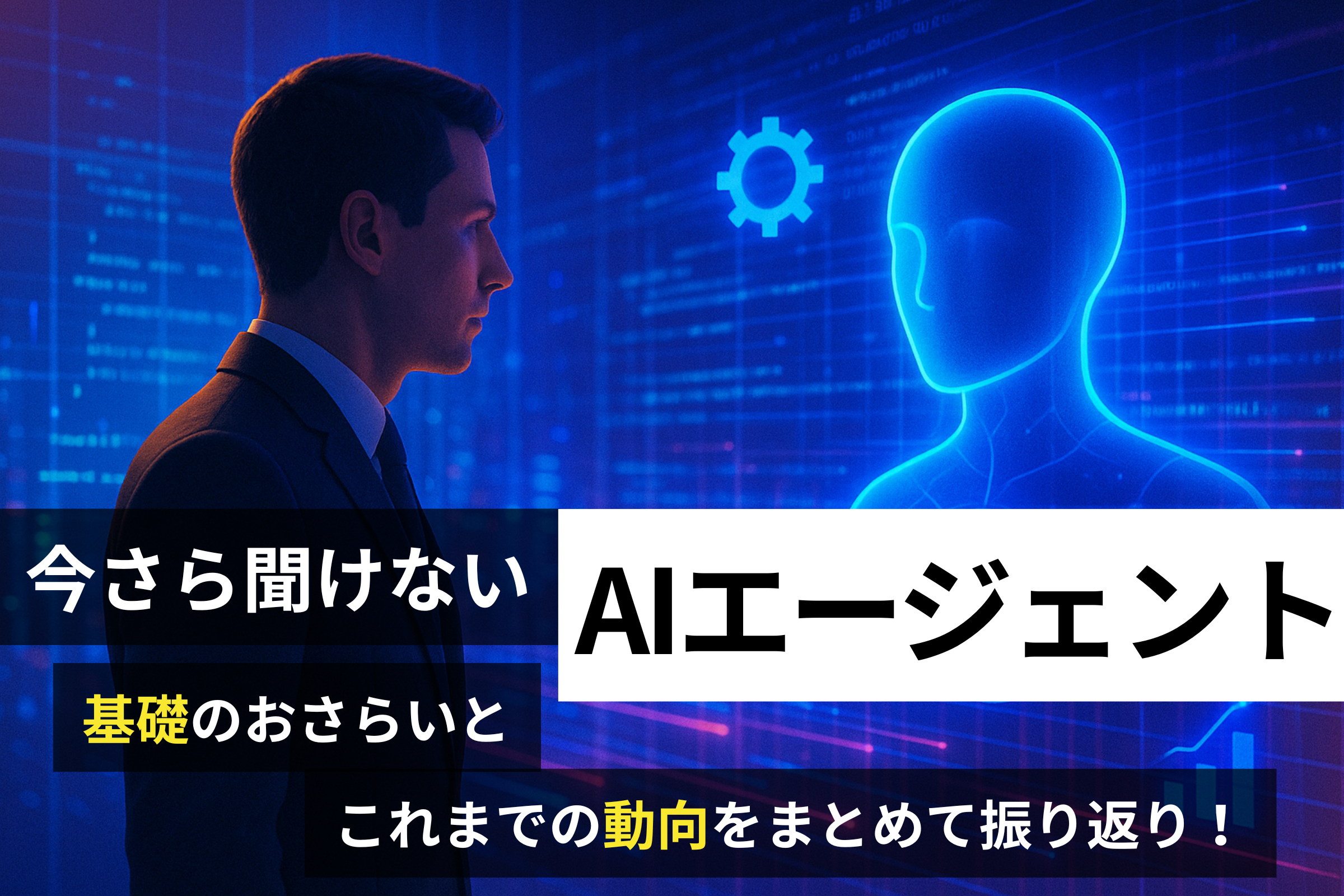

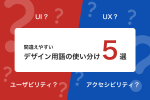

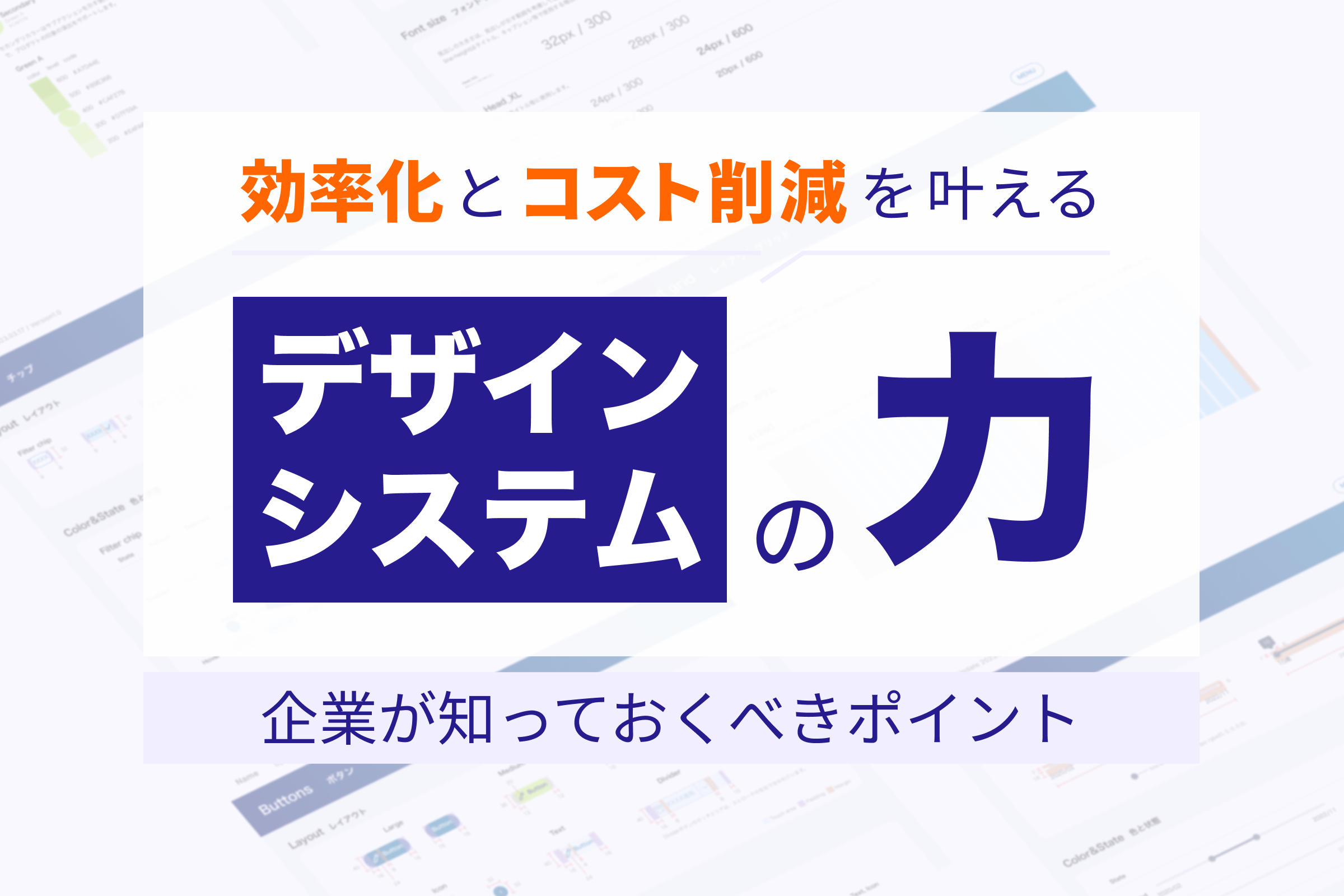
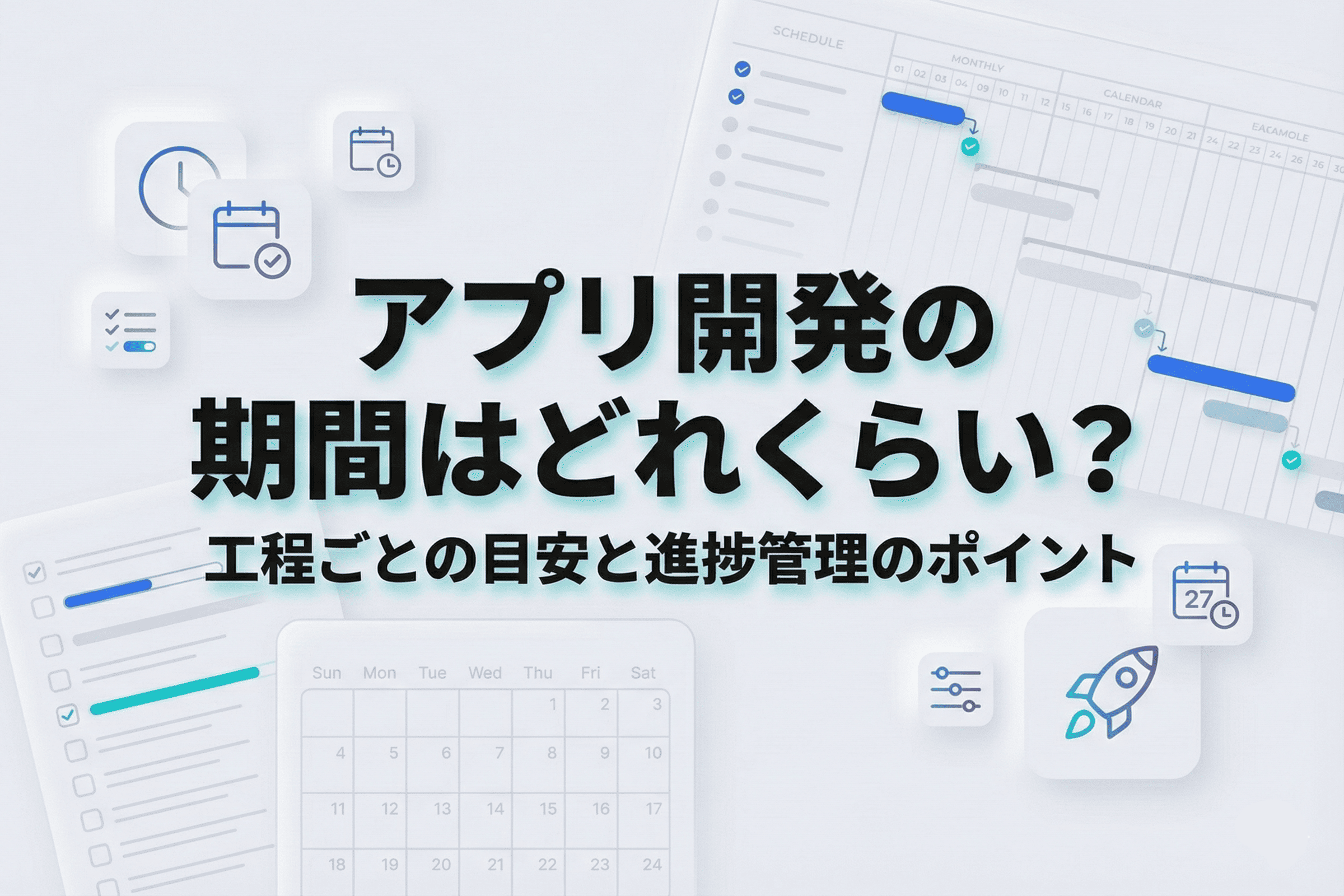

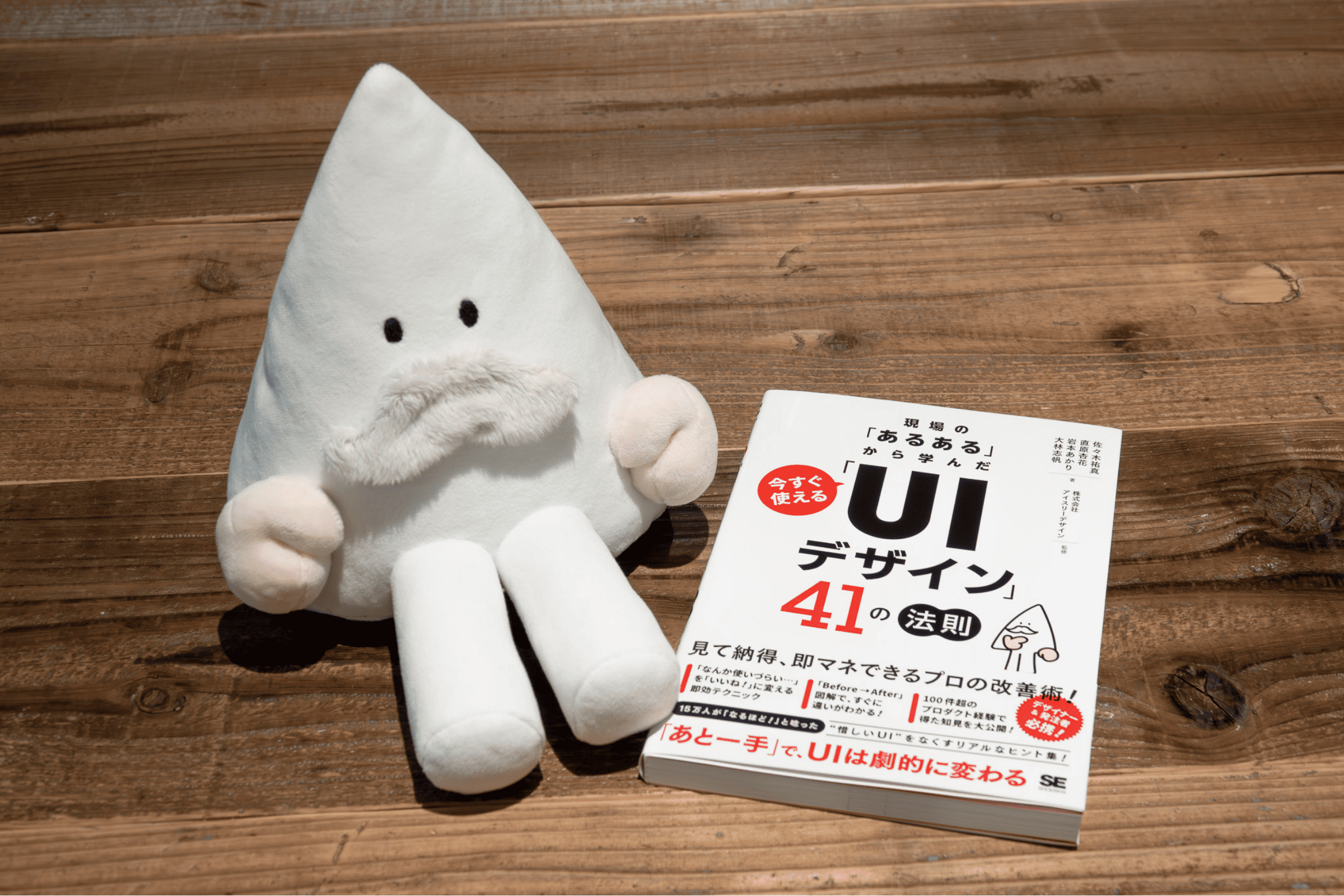
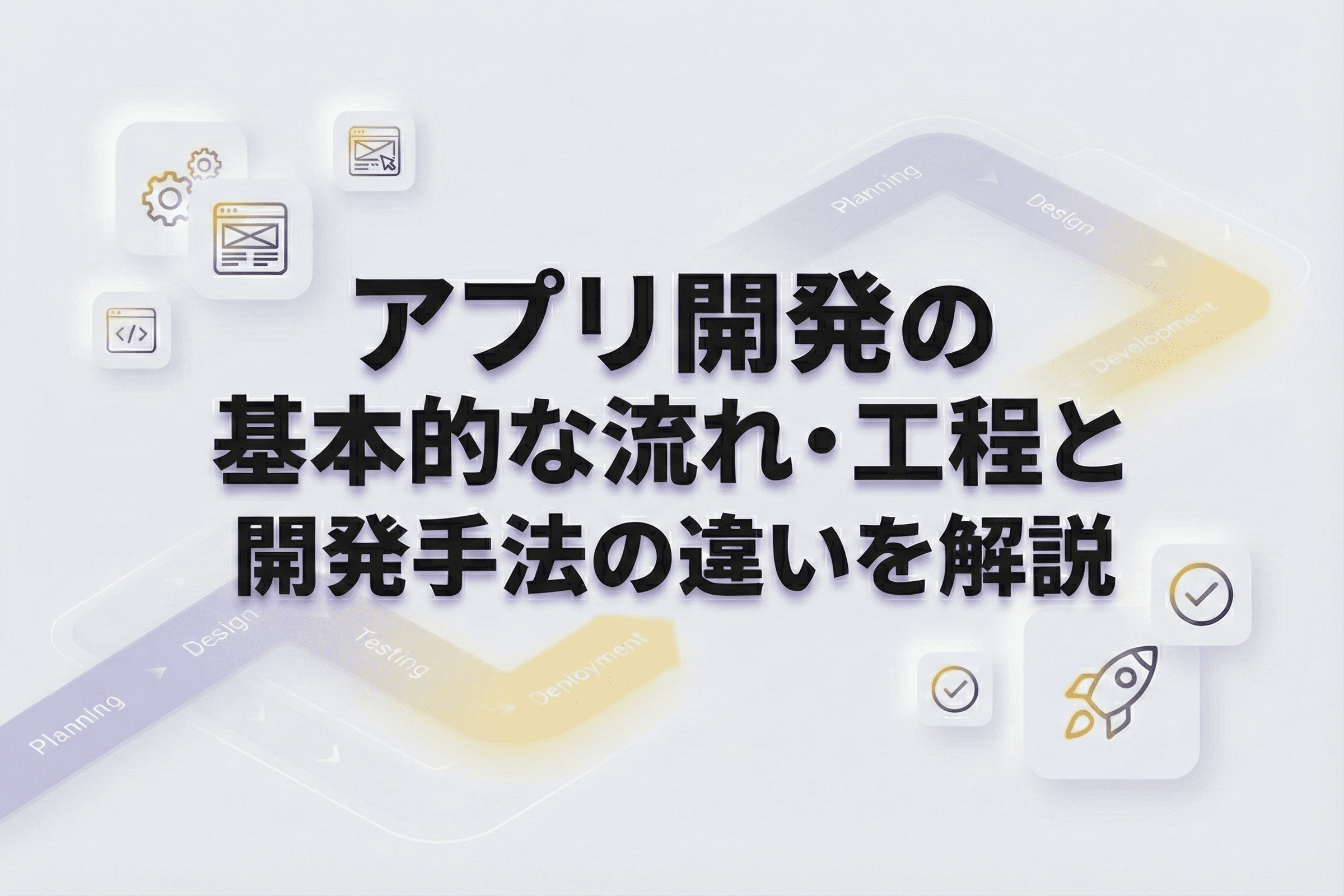
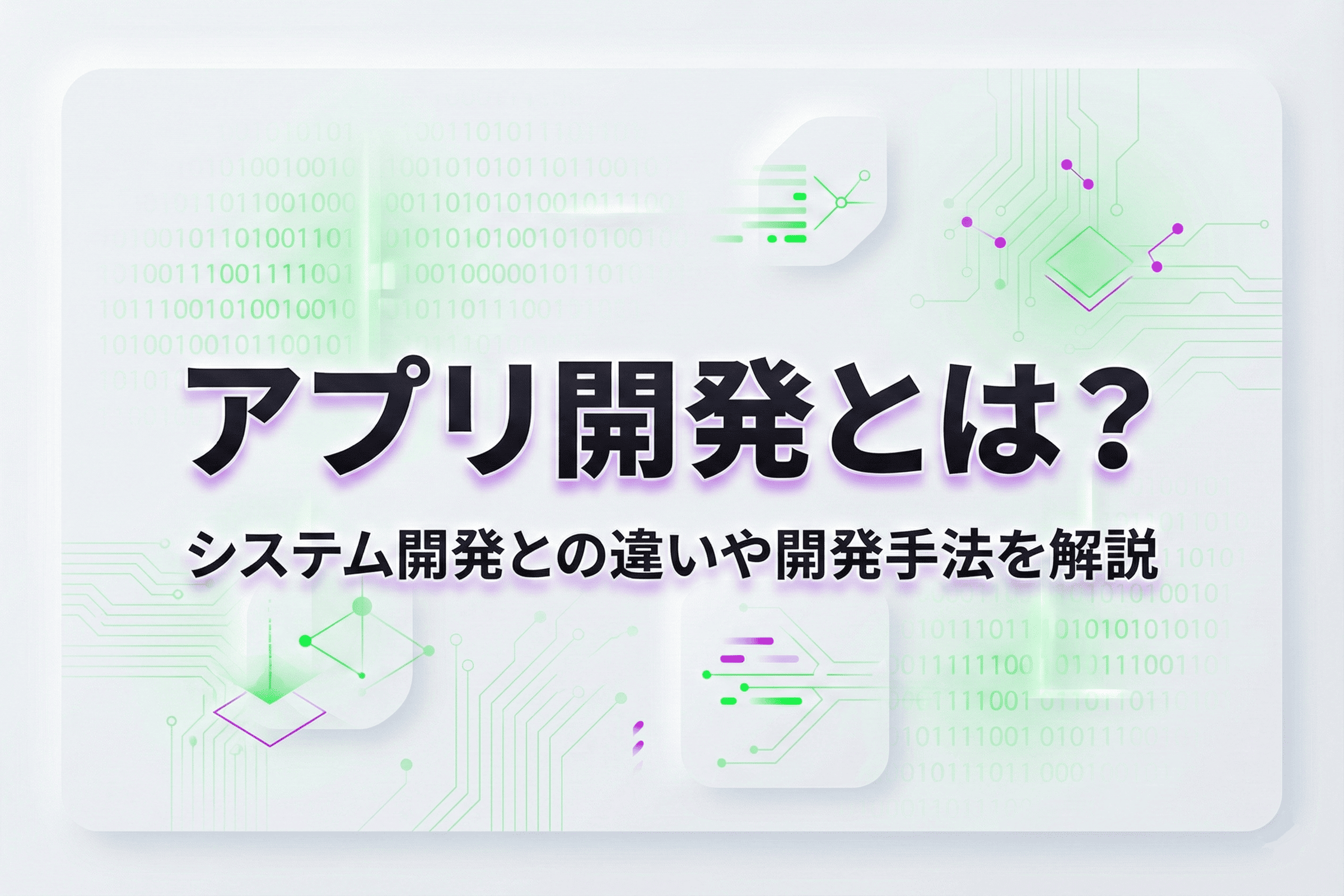
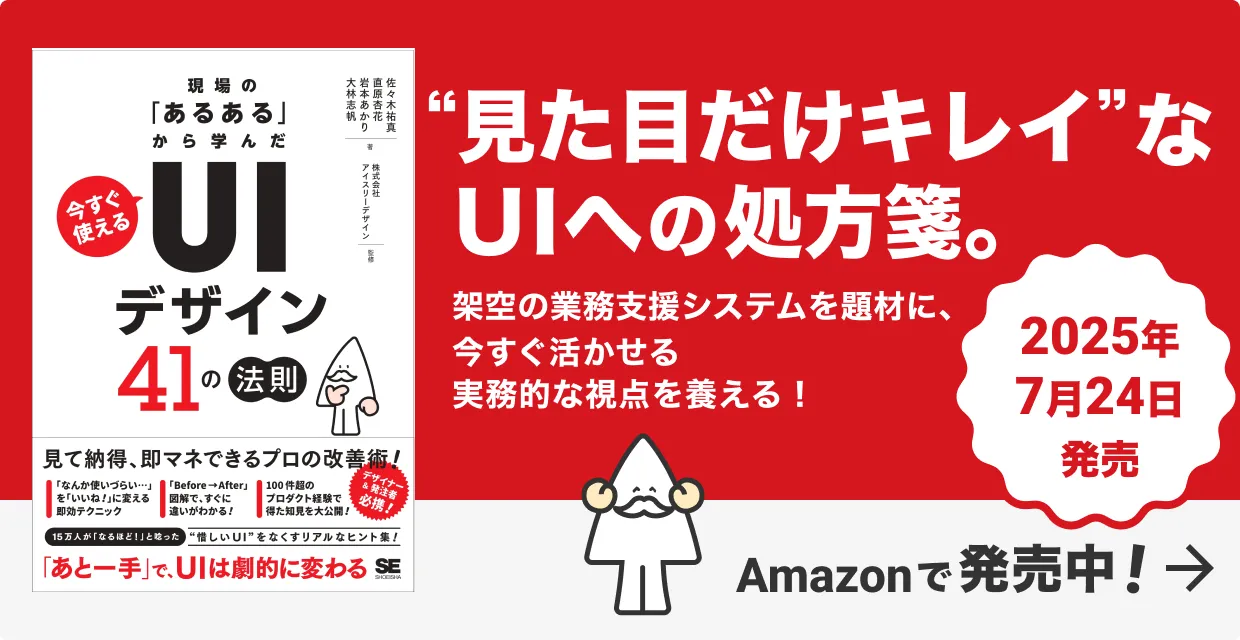
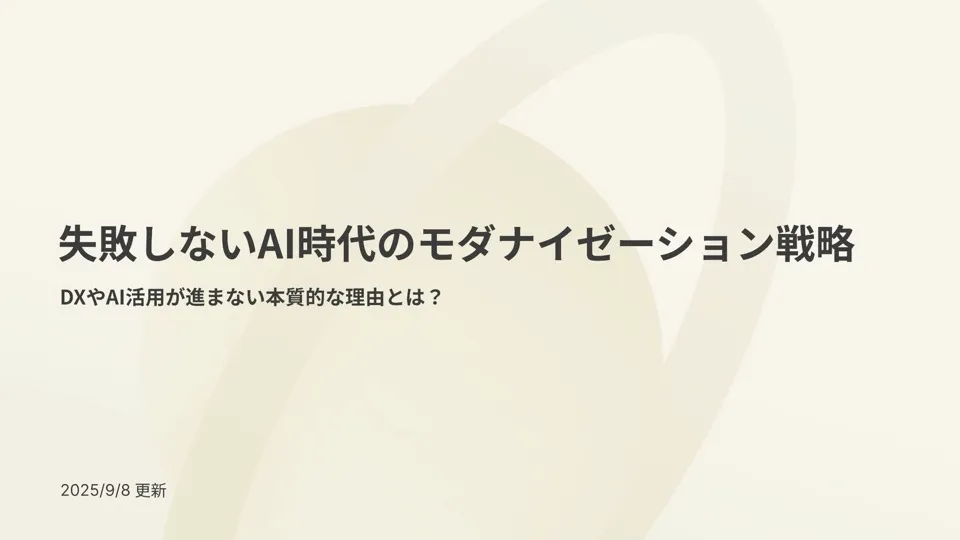
Engineering Handbookはこちらからご覧いただけます。
https://i3design.github.io/engineering-handbook/